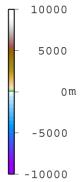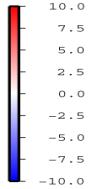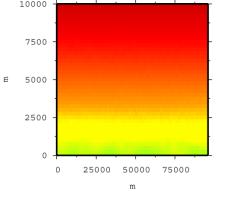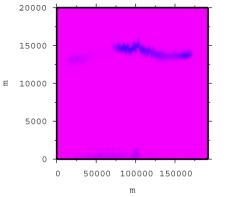}1.1@åCÌ^®ÌÔEóÔXP[
@@@@@@@@@@@@@@@iwêÊCÛwx¬q`õj
1.2@¤ÚI
1.1Å঵½æ¤ÉACÛêÌðxV~
[VðÂ\É·é±ÆÍLvȱÆÅ éB»±ÅA{¤ÅÍAñÃÍwCÛfCReSSðgÁ½RxnÅÌðxV~
[VðÚIÆ·éBµ©µAúlâ«EðÉ^¦éðÍlÍêÊIÉáðÈà̪½¢½ßA·ÌæÌvZÉg¤ÉÍâ誶¶é͸ŠéB»±ÅAlXeBOð¢¤è@ðg¤B
lXeBOÆÍص½¢ÌææèðxðµÄvZµA»ÌvZÊð{V~
[Vµ½¢ÌæÅg¢Aæè¸xÌ¢vZÊð¾éè@Å éB¡ñÍA}1.1Åྵ½~NXP[öxÌðÍðÚIƵĢéÌÅ{ð͵½¢ÌææèàL¢ÍÍÅvZµÄ»ÌÊðg¤B±êÍAêÊIÉCÛêÌqÏðÍlªáðxÈà̵©¾çêÈ¢±ÆðüP·é±ÆªÅ«éB±êÉæèðxV~
[VªÂ\ÆÈéB
ÎÛÌæÍAÌæêѪ°êÄ¢ÄA©ÂðxV~
[Vðµ½êÉARxnÑÌæ¤È¡Gn`ÉÈÁÄ¢é±ÆÆ·éB»±ÅAtß̽ÏÎxª20.8ÌƱëÉ éRÑϪ^[iò§RsAkÜ36x08ª23bEo137x22ª15bjð¡ñÌfnæÆ·éB±Ì^[ÅÍlXÈvª@íðg¢CÛϪAyëϪACO2ZxªzϪðµÄ¢éBÊ^1.2É^[ÌÊ^Aܽ^[üÓÌnæ}ðfÚµ½BÎÛ@ÖÍòRÔÌVCðCÛ¡ÌCÛvîñ©ç²×A2005N83úƵ½B^[üÓÅ̪ð\ÈV~
[Vʪ¾é±ÆªÅ«êÎA¡Gn`ÅÌÀÛÌϪlÆär·é±ÆªÂ\ÆÈéB



@@@@@@@@ Ê^1.2@iãj^[üÓÌÊ^@iºj^[©ç©½i
iòåw21¢ICOEuq¯¶Ôwn¶_vC50TCgÌwwwy[Wæèj
æQÍ
@fÌTvÆè®»
2.1@CReSSÌTv
@@CreSSÍ_XP[©ç\XP[Ì»Û̸xV~
[Vðs¤±ÆðÚIƵÄA¼Ã®åwn
z¤Z^[ÌØØavâ(à)xîñÈwZp¤@\Ìå´ÄuÉæèJ³ê½ñÃÍwCÛfÅ èA¼Ú1Â1Â_ðvZ·éƤɻêªgD»µ½\XP[(KÍ)Ì~
VXeð¸xÅV~
[VÅ«éàÌÅ éB
@ȺÉ{¤Ågpµ½CReSS Ver2.1ÌÁ¥ÆÀ³êÄ¢éïÌIÈ@\ð¢Â©°éB
EÀñvZ@pÉÝv³êĨèAåKÍvZªÀsÅ«éBêûÅA1ÂÌCPU(vZbTGg)¾¯ðp¢éo[WàpÓ³êĨèAPC-UNIXÅàÀsÂ\Å éB
E_¨ßöðÂ\Ⱦ¯Ú×Éæèüê½_fÅ éB
ER[hÍFORTRAN90x[XÅLq³êĨèAÂÇ«ÉDêA©ÂÙÆñÇÌvZ@vbgz[ÅÀsÂ\Å éB
EÍwßöÌîbûö®nÍñÃÍwE³knÅn`ɤÀWnÌ3³ÌæÅvZðÀs·éB
E¹gÌæèµ¢ÉÖµÄ͹gÖAÆ»êÈOɪ¯AÔϪÌ^CXebv𬳵ÄvZðs¤B
E¬ÍX}SXL[Ì1ÌN[W[ܽͬ^®GlM[ðp¢½1.5ÌN[W[Éæép^[[Vð±üµÄ¢éB
EÍwßöÌ]®ÏÍA¬xÌ3¬ªA·ÊηAC³Î·A¬^®GlM[(1.5ÌN[W[Ìê)Å éB
2.2@îbûö®nÌè®»
CReSSfÌxzûö®ÍA^®ûö®(n
Ìñ]ðl¶µ½irGEXg[NXûö®)AMÍwûö®A³knÌA±ûö®A
öC¬äÌ®A_E~
±q̬äÌ®AyÑ_E~
±q̧xÌ®ÅLq³êéB±êç̮ɳܴÜȨßöðè®»µ½àÌÆ«ElÌè®»ªÁíèAfª\¬³êÄ¢éB±ÌfÅÍxCyÀWnÌn}e@(ɽË}@Axg³p~}@A³p~}@)ðÝèµ½èAܽOÌWf[^ðfÌvZÌæÉâÔµ½è·é±ÆàÂ\Å éB
îbûö®
fÌƧÏÍóÔÌÀWA ÆÔ
ÆÔ Å éB±êçÌÖƵÄè`³êé]®ÏÍCReSSÅÌpµÄ¢é³k«Ìûö®ÅÍA¬xÌ
½2¬ª
Å éB±êçÌÖƵÄè`³êé]®ÏÍCReSSÅÌpµÄ¢é³k«Ìûö®ÅÍA¬xÌ
½2¬ª Ƽ¬ª
Ƽ¬ª AîóÔ©çÌ·Êη
AîóÔ©çÌ·Êη AîóÔ©çÌC³Î·
AîóÔ©çÌC³Î· A
öC¬ä
A
öC¬ä A
¨¿(_±âJ±)̬ä
A
¨¿(_±âJ±)̬ä A¨æÑ
¨¿Ì§x
A¨æÑ
¨¿Ì§x Å éB±±Å
Å éB±±Å ÍA
öCÈOÌ
¨¿ÅA_E~
ßöðÇÌæ¤É\»·é©Å»ÌÏ̪ÜèA»êɶÄÔWûö®n̪ÏíéB±±ÅA±êçÌ]®Ï̤¿·ÊƳÍAܽ
¨¿Æ
öCðl¶µ½§x
ÍA
öCÈOÌ
¨¿ÅA_E~
ßöðÇÌæ¤É\»·é©Å»ÌÏ̪ÜèA»êɶÄÔWûö®n̪ÏíéB±±ÅA±êçÌ]®Ï̤¿·ÊƳÍAܽ
¨¿Æ
öCðl¶µ½§x É¢ÄÍAȺÌÃÍw½tA
É¢ÄÍAȺÌÃÍw½tA
@@@@@ (2.7)
(2.7)
ð½·îóÔÆ»ê©çÌηɪ¯éBܽA\LðÈÖÉ·é½ßAÌæ¤ÉÏÏ·µÄ¨B
 (2.8)
(2.8)
@±ÌÏðp¢ÄAe\ñÏðȺÌæ¤ÉÏ··éB
 (2.9)
(2.9)  (2.10)
(2.10)  (2.11)
(2.11)
 (2.12) @
(2.12) @  (2.13)
(2.13)  (2.14)
(2.14)
 (2.15)
(2.15)
§xÈOÌ]®ÏÍ·×ÄÔWûö®nÅ\»³êÄ¢éªAn`ðÜÞê±êçÌ]®Ïð^¦éÔWûö®nÍAObhXP[ɨ¢ÄȺÌæ¤É^¦çêéB

 (2.16)
(2.16)

 (2.17)
(2.17)

 (2.18)
(2.18)
 (2.19)
(2.19)

 (2.20)
(2.20)
 (2.21)
(2.21)
 (2.21)
(2.21)

 @@@@@ @@ (2.22)
@@@@@ @@ (2.22)
±±ÅA®(2.16)` (2.22)Ågpµ½eÌÓ¡ð\2.2ÉÜÆßéB
@@@@@@@@@\2.2@gpµ½ÏÌê
|


|
RIÍW@
@@@@@@@@ @@@ ( @@@ ( :n
Ìp¬xA :n
Ìp¬xA :Üx) :Üx)
|
|

|
óC̹¬
|
|



|
TuObhXP[̬Éæé¬xÌgU
|
|

|

|
|



|
TuObhXP[̬Éæé·ÊܽÍ
¨¿Ì¬äÌgU
|
|



|
·ÊܽÍ
¨¿Ì¬ä̶¬EÁÅ
|
|

|
¨¿Ì¾~(~
)Ì
|
|

|
TuObhXP[̬ÉæéÅÌÌ
¨¿Ì§xÌÏ»
|
|

|
ÅÌ̧x̶¬EÁÅ
|
|

|
¾~(~
)ÉæéÅÌ̧xÌÏ»
|
|

|
lHIÉüê½¹g̸

|
2.3@TuObhXP[ÌgU
lfÍAA±ÌÅ éåCð£UIÈiq_ÌlÉæÁÄ\»·éàÌÅ éBµ©µÀÛÌåCÉÍ»ÌiqÔuæ謳ÈXP[Ì^®ªK¸¶Ý·éB±êÍA»ÌÔuð¢©É¬³µÄà¶Ý·éàÌÅATuObhXP[Ì^®ÆÄÎêêÊÉÍgUƵÄìp·éB
TuObhXP[ÌiqÔuð¢çשµÄàvZÅ«È¢ÌÅ êÎA_IÉTuObhXP[Ì^®ÌÔWûö®ð±±Æªl¦çêéBá¦ÎA¬xðObhXP[¬ªÆ»ê©çÌηɪ¯êÎæ¢B±ÌAObhXP[¬ªÌûö®ÉÍ¢mÊƵÄCmYÍƯlÈηÌ2dÖª»êéÌÅA»êçÌÔWð^¦é®ðl¦éBµ©µA¡xÍ»êçÌÉ3dÖª»êĵܤB¯lÌìðJèÔµÄà³çÉ¢mʪÜÜêA±êçÌûö®nͶȢB±êͬÌñü`«ÉæéàÌÅAKellar
and Friedmann (1924)ÉæÁÄßÄF¯³ê½B±ÌâèðuN[W[âèvÆ¢¤B
±Ì¢ï©ç²¯o·û@Ì1ÂƵÄÍALÀÌÌûö®ðp¢ÄAcèÌ¢mðùmÌÊÅ\·û@ª éB±êÍuN[W[¼èvÆÄÎêA\ñ³êéÖÌÉæèAPÌN[W[A2ÌN[W[AEEEÌæ¤ÉÄÎêéB@@@
TuObhXP[Ì^®Ì\»ÍACReSSÅÍ2dÖðQS«ÌTOÌàÆɽϬxyѬ^®GlM[ÆUí¦ÈÇ̬ðÁ¥t¯éXJ[Êðp¢Ä\»µA±êçÉ¢ÄÌÔWûö®ðÊÉf»·él¦ÌºA1.5ÌN[W[ðp¢Ä¨èAvZ·éɽÁĬ^®GlM[É¢ÄÌÔWûö®ªKvÉÈéB
2.3.1@¬AÌp^[[VÆgUÌè®»
@@ß2.2.2Åq×½n`ɤÀWnÅÌî{ûö®É¨¢ÄA^®ûö®A·ÊÌ®A
öCÆ
¨¿Ì¬äÌ®A¨æÑA
¨¿Ì§x̮ɻêégU(¬¬Ì) ÍQS«W
ÍQS«W ÆQgUW
ÆQgUW ÉæÁÄ\³êA»êð]¿·éû@ðQS«fÆ¢¤BȺÌßÅÍAÌ2ÂÌQS«f̤¿¡ñÌÀ±ÅÌpµÄ¢éãÒÌà¾ð·éB
ÉæÁÄ\³êA»êð]¿·éû@ðQS«fÆ¢¤BȺÌßÅÍAÌ2ÂÌQS«f̤¿¡ñÌÀ±ÅÌpµÄ¢éãÒÌà¾ð·éB
E X}SXL[Ì1ÌN[W[
E ¬^®GlM[ðp¢½1.5ÌN[W[
2.3.2@QS«fi¬^®GlM[ðp¢½1.5N[W[j
@@^®ûö®ÌgUÍAÍe\ ðp¢ÄÌæ¤É\»³êéB
ðp¢ÄÌæ¤É\»³êéB
 @@@@(2.23)@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@(2.23)@@@@@@@@@@@@@@@
¯lÉ ÉÖµÄ௶æ¤É\»³êéB±±ÅAÍe\
ÉÖµÄ௶æ¤É\»³êéB±±ÅAÍe\ ÍA¹ñfÍÆCmYÍƯlÈàÌ©çÈéBCmYÍƯlÈàÌÍObhXP[¬ª©çÌÏ®¬ª©çÈéÌÅA½ÏÊðp¢½`®É½ç©Ìf»ð·éKvª éB»±ÅA¹ñfÍ©çÌÞÅAS«Wðp¢½ùzgUÌ`®É\·±Æðl¦éÆȺÌæ¤ÉÈéB
ÍA¹ñfÍÆCmYÍƯlÈàÌ©çÈéBCmYÍƯlÈàÌÍObhXP[¬ª©çÌÏ®¬ª©çÈéÌÅA½ÏÊðp¢½`®É½ç©Ìf»ð·éKvª éB»±ÅA¹ñfÍ©çÌÞÅAS«Wðp¢½ùzgUÌ`®É\·±Æðl¦éÆȺÌæ¤ÉÈéB
@  @
@ @@@@@@@(2.24)
@@@@@@@(2.24)
@@@@
SijFÏ`¬xe\
·ÊA
öCÆ
¨¿Ì¬äAyÑA
¨¿Ì§xÌgUÉ¢ÄÍA»êçÌÏð Åã\µÄ
Åã\µÄ
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.25)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.25)
Ìæ¤Éè®»·éB±±ÅA C
C Í
Í ûüÌA
ûüÌA Í
Í ûüÌAã®ÉY·éXJ[Ê
ûüÌAã®ÉY·éXJ[Ê ̪qgUƬ(TuObhXP[Ì)tbNXÅAùzgUÌ`®Å
̪qgUƬ(TuObhXP[Ì)tbNXÅAùzgUÌ`®Å
 @@@@@@@@@@ (2.26)
@@@@@@@@@@ (2.26)
 (2.27)
(2.27)
 (2.28)
(2.28)
Ìæ¤É^¦çêéB
¡ñÌÀ±Égpµ½1.5ÌN[W[ÅÍA Ìèɬ^®GlM[É¢ÄÌÔWûö®ðp¢éB±Ì¬^®GlM[Íe¬x¬ªÉ¢ÄA½Ï¬©çÌη h
Ìèɬ^®GlM[É¢ÄÌÔWûö®ðp¢éB±Ì¬^®GlM[Íe¬x¬ªÉ¢ÄA½Ï¬©çÌη h ðtµÄA
ðtµÄA
@ @@@@@@@@(2.29)
@@@@@@@@(2.29)
Æ\³êA»ÌÔWûö®ÍAÌæ¤É^¦çêéB

 @@(2.30)
@@(2.30)
±±ÅA±ÌßÉgpµ½LÌÓ¡ð\2.3ɦ·B
@@@@@@@@@@@@@@ @\2.3
|
L
|
Ó¡(®)
|
|

|
ÊuGlM[Æ^®GlM[ÌÏ·
|
|

|
UíÌW3.9
or 0.93@@(3.9:źwA0.93:»êÈO)
|
|

|
 ûü̬^®GlM[ÌtbNX ûü̬^®GlM[ÌtbNX
|
|

|
½ûü̬·XP[
|
|

|
¬^®GlM[ÉηéQS«W
|
³ðÍÉæèQS«W ͬ^®GlM[
ͬ^®GlM[ ÌÖƵÄA
ÌÖƵÄA
 @@@@@@@@(2.31)
@@@@@@@@(2.31)
@
 @@@@@@@@(2.32)
@@@@@@@@(2.32)
Æ^¦çêéB±±ÅA Í»ê¼ê
½E¼Ì¬·XP[Å éBCReSS
Í»ê¼ê
½E¼Ì¬·XP[Å éBCReSS
ÅÍiqÔuª
½Æ¼ÅÙÚ¯¶êÆå«ÙÈéêÆÅA^¦é¬·XP
[Ìlªá¤BȺɦ·B
ÙÚ¯¶êÉÍA
@@@ @@@(2.33)
@@@(2.33)
Ìæ¤É^¦çêéB½¾µA
 @@@@@(2.34)
@@@@@(2.34)
 @ @@(3.35)
@ @@(3.35)
Å é( Í»ê¼êÌiqÔu)BܽAå«ÙÈéêÉÍA
Í»ê¼êÌiqÔu)BܽAå«ÙÈéêÉÍA
 @ @@@@ @@@(2.36)
@ @@@@ @@@(2.36)
 @@@ @@@(2.37)
@@@ @@@(2.37)
Ìæ¤É^¦é±ÆªÅ«éB½¾µA
 @@@@@@@@@ (2.38)
@@@@@@@@@ (2.38)
 (2.39)
(2.39)
2.4@n\Êßö
2.4.1@n\ÊÌMûx
n\Ê©çnÉü©¤n`±Mð ƵA³¡úËtbNX
ƵA³¡úËtbNX A°MtbNX
A°MtbNX AöMtbNX
AöMtbNX Æ·éÆ\ÊMûxÍA®(2.41)Å\³êéB
Æ·éÆ\ÊMûxÍA®(2.41)Å\³êéB
@@ =
= +
+ +
+ @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ @(2.41)
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ @(2.41)
±±ÅA
 (2.42)
(2.42)
 (2.43)
(2.43)
 F³¡úËÊtbNX@@@@@
F³¡úËÊtbNX@@@@@
 FúËÊ@
FúËÊ@
 FúË̽ËÊ
FúË̽ËÊ 

 FåCÌúËÊ
FåCÌúËÊ
@@@@ Fn\ÊÌúÂÔOúËÊ
Fn\ÊÌúÂÔOúËÊ
 FÔOúËÉηén\ÊÌËo¦@{fÅÍPÆ·éB
FÔOúËÉηén\ÊÌËo¦@{fÅÍPÆ·éB
 Fn\Ê·x
Fn\Ê·x ÉηéÌúËÊ
ÉηéÌúËÊ
@@@@ FAxh
FAxh
@ÆÈéB
@³¡ºüZgúËÉ¢Ä
 (2.44)
(2.44)
@@@
 FåCÌã[ÉB·éúËÊ
FåCÌã[ÉB·éúËÊ
@@ F¾zè@à1367[W/2]@
F¾zè@à1367[W/2]@
@@ F¾zÌV¸p
F¾zÌV¸p
@°VÌúËÊÍA
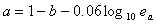 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.45)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.45)
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.46)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.46)
@@(1

30 [hPa]Fn\ÊtßÌ
öC³)
30 [hPa]Fn\ÊtßÌ
öC³)
ƵÄAÌæ¤É·éB

 (2.47)
(2.47)

 (2.48)
(2.48)
³çÉA_ÌøÊðæèüêAAxhðl¶·éÆAn\ÊÉzû³ê鳡ºüZgúËÍA
@@
@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2.49)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2.49)
Å éB½¾µA
@@ Fáw_Ì_Ê
Fáw_Ì_Ê
@@ Fw_Ì_Ê
Fw_Ì_Ê
@@ Fw_Ì_Ê
Fw_Ì_Ê
@@ Fáw_ÉæézûƽËÌøÊ
Fáw_ÉæézûƽËÌøÊ
@@ Fw_ÉæézûƽËÌøÊ
Fw_ÉæézûƽËÌøÊ
@@ Fw_ÉæézûƽËÌøÊ
Fw_ÉæézûƽËÌøÊ
@@@@
@Æ·éB
@°MtbNX EöMtbNX
EöMtbNX É¢Ä
É¢Ä
 @ (2.50)
@ (2.50)
 (2.51)
(2.51)
@@@ FåCæPwÆn\Ê(n·æPw)
FåCæPwÆn\Ê(n·æPw)
 FPÊÌÏÌóCÌMeÊ
FPÊÌÏÌóCÌMeÊ
 FMÆ
öCÉ¢ÄÌoNW(³³)
FMÆ
öCÉ¢ÄÌoNW(³³)
 F°MAÌð·¬x@i
F°MAÌð·¬x@i F¬j
F¬j
 FåCæPwÌC·
FåCæPwÌC·
@@@ Fn\Ê·x
Fn\Ê·x
 FöUW
FöUW
 FåCæPw̬ä
FåCæPw̬ä
 F
F ÉηéOa¬ä
ÉηéOa¬ä
ÆÈéB
2.4.2
¼En\ÊtbNX
ܸA¼tbNXÍÚn«EwàÅêèÅ éÌÅAn\Êɨ¯étbNXð©Ïàé½ßÉÍAÚn«EwÌ é³É¨¯étbNXð©ÏàêÎæ¢B^®ÊÌtbNXÍA
 (2.52)
(2.52)
Å éB±±ÅA(2.50),(2.51),(2.52)É é ÍoNWÅ èALouis et
al. (1980)ÌXL[ðp¢Ä\»³êéB
ÍoNWÅ èALouis et
al. (1980)ÌXL[ðp¢Ä\»³êéB
 (2.53)
(2.53)
 (2.54)
(2.54)
±±Å (=0.4)ÍKarmanèA
(=0.4)ÍKarmanèA ÍåCæ1w̳A
ÍåCæ1w̳A Í^®ÊÌexA
Í^®ÊÌexA ÍMÆ
öCÌexA
ÍMÆ
öCÌexA ÍRichardsonÅ éBoNWÉ©©éW
ÍRichardsonÅ éBoNWÉ©©éW àexÆRichardsonÌÖÅAÌæ¤É^¦çêéB
àexÆRichardsonÌÖÅAÌæ¤É^¦çêéB
sÀèÈê( <0)A
<0)A
 (2.55)
(2.55)
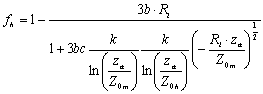 (2.56)
(2.56)

@ÀèÈê( >0)A
>0)A
 (2.57)
(2.57)
 (2.58)
(2.58)
 (2.59)
(2.59)
±±ÅA^®ÊÆME
öCÉ¢ÄÌexA ,
, ÍÌæ¤É^¦çêACãÌexÍvZÌeXebvÉC³³êéB
ÍÌæ¤É^¦çêACãÌexÍvZÌeXebvÉC³³êéB
@@@@@@@@@
|
|
¤ã@@@@@@@@@@@@@@@@@Cã@@@@@@@@@@@@@@
|
|

|
f[^Zbg©ç^¦é@@@@@@@@ ÌÖƵÄvZ·é ÌÖƵÄvZ·é
|
|

|
êèl(0.1m)@@@@@@@@@@CãÌ Ư¶Æ·é Ư¶Æ·é
|
æRÍ
@fÌÝèð
3.1
fÝèÉ¢Ä
¡ñÍúðÆ«EððV~
[VAÅÍCÛ¡ÌqÏðÍlðAlXeBOð·éV~
[VBÅÍV~
[VAÌÊðg¤±ÆÉ·éB»µÄAºLɤÊÌfÝèÆ»ê¼êÌfÝèð¢½BȺ±êçÌÀ±¼ðAÆBÆÄÔ±ÆÉ·éB
À±`ÆÀ±aɤÊÈÝèÍȺÌPPÚÅ éB
E
iqiX~Y~Zj¥¥¥99~99~60
E V~
[VÔ¥¥¥2005N83ú9F00`15F00ÔÌ6Ô
E X|Ww¥¥¥¤ÊAãÊ»ê¼ê10wÃÂ
E Of[^Ö̧¥¥¥¤ÊAãÊÆàɧµÄA³êɤÊɨ¯é¿Ê²®ðÀs·é
E «E𥥥¤ÊAã[Aº[ÆàÉÅèÇ«Eð𠽦éB
E nßö¥¥¥TðUwÆèAźwÌ·xÉ300.5Kð^¦éB±êÍ1971N©ç2000
@@@@@@@NÜÅÌòɨ¯éW̽ÏC·ð^¦éiÈN\2005Nj
E
CÊßö¥¥¥CÊ
·Éêè·xð^¦éB±êÍCÛ¡ÌCÛvîñæèWRúÌC
@@Ê
·}Ų×Ä298jƵÄ^¦éB
E ú·Ê¥¥¥ÝèµÈ¢
E ¼ûüÌÔϪ@¥¥¥KEXÌÁ@æèA¼ûüAð@·é
E TuObh̬ßö¥¥¥TuObhXP[Ì^®GlM[ðp¢½1.5ÌN[W
@[f
E _÷¨ßö¥¥¥XðÜÞoNûÌp^[[V
E Wf[^cln}50mbV
iWjiÚµÍæSÍÅj
E ynpf[^cGLCCiÚµÍæTÍÅj
@ܽAeÀ±²ÆÉÏX·éÝèÍ»ê¼êȺÌæ¤ÈàÌÅ éB
@qV~
[VAr
@@iqÔuiX,Y,Zj¥¥¥2000m,2000m,300m
@@fÌúlAOCÛf[^¥¥¥\ðÍliÚµÍæUÍÅjð^¦é
¹g[hÉÖWµÈ¢¥¥¥5b
¹g[hÉÖW·é¥¥¥0.5b
qV~
[VBr
iqÔuiX,Y,Zj¥¥¥1000m,1000m,150m
fÌúlAOCÛf[^¥¥¥V~
[V`ÌÊð^¦éB
¹g[hÉÖWµÈ¢¥¥¥2.5b
¹g[hÉÖW·é¥¥¥0.25b
3.2
CReSSÉ^¦éeíf[^ÌÀÑûÉÖ·éÓ_
CReSSÉWf[^Aynpf[^AOCÛf[^ð^¦éf[^Ì`®ÆA»ÌÀ×ûÉ¢ÄྷéBðxV~
[Vð·éÉÍAcåÈf[^𵤱ÆÉÈéÌÅAPCÌÛ¶eÊÆüoÍ̬xðl¦éƵÅàt@CTCYð¬³Å«½Ù¤ªÇ¢BܽACReSSÉ^¦éf[^`®ÍÁÉwèÍÈ¢ªACReSSÌ\[XvOðÏX·éKvªoÄé½ßAftHgÌoCi`®Å^¦é±ÆÉ·éB±ÌoCi`®Ìt@CÍA¼Út@CðJ¢ÄAf[^ðmF·é±ÆªÅ«È¢ÌÅAoCif[^ðmF·é½ßÌvOàKvÆ·éB{¤É¨¢ÄàAåÊÈf[^𵤽ßAG[`FbNƵĽxàmFvOðgÁ½B
@@ÉCReSSªÇÌæ¤ÉoCit@C©çf[^ðÇÝñÅ¢©ðྷéBWf[^Aynpf[^ÉÖµÄÍñ³f[^Å èAOCÛf[^yÑlXeBOð·éÛÉKvÆÈéÀ±AÌðÍÊÍO³f[^Å éBȺÌ}3.2.1Æ}3.2.2ðg¢ÈªçྷéB
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|



@}3.2.1@ñ³@@@@@@@@@@@@@}3.2.2@O³
@@ܸAñ³i5~5jAO³i5~5~3jÌf[^ª éÆl¦éB^¦éf[^ªñ³f¾Á½êA}3.2.1ÌÔÉÇÝñÅ¢ÌűÌÔÅoCit@CÉlðü͵ĢKvª éB
ܽO³f[^ÌêÍZPÉ éñ³f[^©çÇÝÞÌÅ»ÌÔÉÀ×éBáƵÄO³ÀW(x,y,z)=(5,3,2)Å êÎAêiÚÌf[^ðÇÝÝA»ÌãaÌ éñiÚðÇÝÞ±ÆÉÈéÌÅ25+1540ÔÚÉf[^ª ê΢¢B
Èã̱ÆÉÓµÄAef[^ðÏ··éKvª éB
ܽoCit@CÌáð}3.2.3ɦµ½BPÂÌf[^ðÛ¶·éÌÉSbyteKvÈÌÅA±Ìæ¤ÉP0ÂÌf[^ðÀ×½¯êÎ40byteKvÆÈéBæÁÄ}3.2.2ÅÍA
5~5~3~4300byte
ÆÈéB
|
15
|
19
|
79
|
-65
|
25
|
38
|
97
|
42
|
89
|
1
|
@@@@@@@@@@@}3.2.3@oCit@CÌ\¢@(40byte)
æSÍ@CReSSÉ^¦éWf[^
4.1@ln}50mbV
iWj
@@yn@ª§sµÄ¢é25çªÌ1n`}É`©êÄ¢éü©çxNgf[^ð쬵A»ê©çvZÉæÁÄß½lWf(DEM: Digital
Elevation Model)Å éB
@@25çªÌ1n`}iQbV
joxûü¨æÑÜxûüÉA»ê¼ê200ªµÄ¾çêéeææiP/20תbV
A25çªÌ1n`}ãÅñ2~22jÌSÌWªL^³êÄ¢éBWÌÔuÍÜxiìkjûüÅ1.5bAoxûüÅ2.25bÆÈèAÀ£Åñ50mbV
Å éB
4.2@ln}50mbV
iWjÌÏ·yÑÍÍ
@@¡ñÌvZðs¤ÛÉñ200lûÌWf[^ÉÏ··é±ÆªKvÅ éBܸÍKvÈWf[^ðÂȬí¹A©ÂCReSSÌÝèɶ½t@Cð쬷éKvª Á½ÌÅAFortran77ðg¢vOð쬵½BvOÍt^1.1A1.2ÉfÚµ½BܽAn`ªCÅ éêAWf[^ª-999.9mÆÈÁÄ¢éªA±ÌÜܾÆCReSSªW-999.9Énʪ¶Ý·éÆF¯µCÝü¢ÉâǪ éæ¤ÈV
~[VÉÈéÌÅÍÈ¢©Æl¦A-1ÉC³µ½BܽWf[^ÍV~
[VÍÍæèå«ÈÌæðgpµÈ¯êÎÈçÈ¢B
iqF4800~4800
iqÔuFìkûü¥¥¥1.5b
@@@@@¼ûü¥¥¥2.25b
|
|

@@@@@@@}4@CReSSÉ^¦éWf[^ij
æTÍ@CReSSÉ^¦éynpf[^
5.1@GLCCÉ¢Ä
@@GLCCÆÍAUSGSEDCANebraska-LincolnåwAthe Joint Research Centre of the
European Commision Éæè쬳ê½1kmiqÌyní¢EA¶f[^ZbgÅ éB
@@fÌüÍf[^ƵĻÌÜÜg¦éæ¤É6íÞ̤ÊfÉí¹½yní¢EA¶^CvÌf[^ZbgªpÓ³êÄ¢éBf[^ÍA¤nÌiqðø¦IÉæ赤½ßÉInterrupted Goode Homolosine }@ªp¢çêÄ¢éB40031~17347ÌiqÌyní¢EA¶^Cvª1iq1oCgÅi[³êÄ¢éB
5.2@GLCCÌynpf[^Ï·yÑÍÍÉ¢Ä
@@GLCCÌf[^©çRsüÓÌynpðÇÝæÁ½ ÆÉARi2004jÌ_¶ðQlɵÄ\3.3Ìæ¤Éeynpf[^Ìp[^ðÝèµ½B»Ìynpf[^ð\¦·éÆ}5Ìæ¤ÉÈéB¡ñA^¦éynpf[^ÍAWf[^Ư¶V~
[VÍÍæèå«ÈÌæÉ쬵ȯêÎÈçÈ¢BܽAAÍLÍÍÈÌæÅV~
[Vð·é½ßAWf[^Æ̸êªÈ¢æ¤ÉÌæªÙÚdÈéæ¤ÉÜxoxðÝèµÄÏ·µ½B
\3.3@eynpÌp[^
|
@
|
Ê
|
áÊ
|
ss
|
c
|
kìn
|
XÑ
|
|
CReSSÔ
|
-1
|
5
|
11
|
17
|
23
|
29
|
|
Axh
|
0.06
|
0.8
|
0.12
|
0.17
|
0.2
|
0.09
|
|
öUW
|
1.02
|
1.05
|
0
|
0.65
|
0.3
|
0.26
|
|
eximj
|
0.00033
|
0.00014
|
1
|
0.1
|
0.155
|
0.65
|
EAxh¥¥¥¨ÌÉÂõªüË·éÛÌAüËõÌtbNXƽËõÌtbNXÌä
EöUW¥¥¥n\ÊÌötbNXƯ·xÌötbNXÌä
Eex¥¥¥Cð\·óCÍwIex





iq@F289~253Â
iqÔuF30b
|
|
 @@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@
@@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@
æUÍ@CReSSÉ^¦éOCÛf[^
6.1@\ðÍlÉ¢Ä
\ðÍlÆÍACÛ¡ÉæÁÄìçêACÛƱxZ^[ÉæÁÄL¿Åzz³êÄ¢éqÏðÍlÅAS¢EÌCÛϪf[^Æl\ñfÌ\zl©çR³IÉK¥³µªzµ½iq_ãÌCÛvfÉÏ·µ½lÅ éBðÍlÍ00,06,12,18UTCÌPúSñÌðͲÆÉAt@CÉi[³êÄ¢éB»ê¼êÌðÍlÉÍACÊC³AWI|eVxAC·AμxA¬i¼ûüAìkûüjªÜÜêÄ¢éBPR[hÍAPÂÌCÛvfÉæéQ³iq_f[^ÛCÛÊñ®GRIBÉ]ÁÄLqµ½àÌÅ éBPt@CÍA¯¶ðÍÌCÛvfE
½ÊÌgÝí¹É¢ÄÌR[hðA±³¹½àÌÅ éB
6.2@\ðÍlÌf[^Ï·yÑÍÍÉ¢Ä
\ðÍlÍGRIB`®Ìt@CÉi[³êÄ¢ÄA±±©çf[^ðæèo·½ßÉwgribÆ¢¤f[^Ï·c[ðgpµ½iwgribÉ¢ÄÍæVÍÅྷéjB±êÉæèeC³ÊxÅÌðÍlðCReSSÌÝèɶÀÑÖ¦AÐÆÂÌt@Cɳ¹½B»ÌÛÉAn\ÊÌf[^É¢ÄÍAeiqÅÌC³f[^ªû^³êĢȩÁ½ÌÅAgpµÈ©Á½BμxÉÖµÄÍAC³Ê250hPa©ç10hPaÌÍͪû^³êĢȩÁ½ªAÙÚO¾Æl¦Äf[^ð쬵½BܽA100ð´¦éf[^É¢ÄÍACReSSÅÇÝޱƪūȢÌÅA99.99Éu«·¦é±Æɵ½Bf[^ÌæÉ¢ÄÍA\ðÍlÌû^næªú{üÓæÈÌÅ»ÌÜÜgpµ½BܽAoCi`®ÉÏ·µ½ÛÌAf[^̪í©çÈ©Á½½ßnãÊÅÌC·Ìf[^ðg¢A}»·é±ÆÅmFðµ½B}6Í»ÌmF}Å éBCReSSÌOCÛf[^ðµ¤ÛÌf[^ÌÀÑûǨèÉ\¦µ½çAú{ñª\¦³ê½Ìųµ¢Æ»fÅ«éB

úF2005N83ú
UTC@00F00A09F00
iqF361~289~20Â
in\Êf[^Íj
iqÔuF10kmi
½ûüj
|
|

@@@@@@@@}6@nãÊɨ¯é·xªz}ij
æVÍ
@ì¬vOAyÑgpc[Ìàe
V~
[Vð·éÉ ½èKvÆÈÁ½vOAyÑ¡ãCReSSðgÁ½¤Éð§ÂvOðÐî·éB{¤Í±êçÌvOì¬É½åÈÔðïâµÄµÜÁ½ªA¢¸êà{¤ÅÍKvÈàÌÅ èA¡ãCReSSðgÁ½¤ð·éÒàp·é±ÆªÅ«éB
7.1@Wf[^ì¬vO
lXeBOð·é½ßÉLåÅ©ÂðÈWf[^ðgp·éKvª Á½B»±ÅAæSÍÅÐîµ½Wf[^ðCReSSÉ^¦é±ÆªÅ«éæ¤ÉÏ··évOðJµ½BܽAÏ·³ê½Wf[^ª³µ¢©ðmF·é½ßÉAÀÛÉ}Å\·½ßÌmFf[^àí¹Ä쬵½Bf[^ÔuÍæSÍŦµ½Æ¨èÅiqª200~200A1600~1600A4800~4800Ìf[^ðìé±ÆªÅ«éæ¤ÉRÂÌvO~Oðµ½B
ܸàÆàÆÌWf[^iȺAln}50mbV
iWj̱Æð³·jÍ}7.1.1Ìæ¤É énæ²ÆÉÔªèUÁÄL³êÄ¢éB200~200Æ¢¤ÌÍA±ÌÌæÌQ
ÌÔÌnæÌð³·BÂÜèA±ÌÌæÉÍAñ50lûÌnæ²ÆÉWf[^ª èA»êª200~200 é±Æð¦·B»µÄ200~200²ÆÉAÐÆÂÌ»ÌÌæð8~8ÂWßé±ÆÅ1600~1600ÌWf[^ðìé±ÆªÅ«éB³çÉA4800~4800Æ¢¤ÌÍ1600~1600ð3~3ÂWßé±ÆÅÅ«éWf[^̱ÆÅ éB
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
00
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
@@@@@@@@@@@1600~1600@@@@@@@@@@@@@@@200~200
|
bV
R[h
|
R[hÔ
|
@W@@l@
|
|
??????
??????
??????
E
E
E
??????
??????
|
001
002
003
E
E
E
199
200
|
1@2@3@4@EEE@199@200
1@2@3@4@EEE@199@200
1@2@3@4@EEE@199@200
E
E
E
1@2@3@4@EEE@199@200
1@2@3@4@EEE@199@200
|
@7.2@WGRIBiGRIBf[^Ï·c[jðpµ½OCÛf[^Ìì¬
¡ñAOCÛf[^ƵÄgpµ½CÛ¡Ì\ðÍlÍAGRIB`®ÅÛ¶³êÄ¢½B±Ì`®Ìt@Cðæ赤êAWGRIBÆ¢¤c[ªKvÆÈéBWGRIBÆÍNCEPiAJÌ«\ªZ^[jÌWesley Ebisuzaki ÉæÁÄ쬳ê½C¾êvOÅ èAC¾êðRpCÅ«é«Èçgp·é±ÆªÂ\Å éªAUNIX«Ågpµ½ûª³ï¾ÆvíêéBg¢ûÍR}hCÅAWGRIBÌ ÆÉWGRIBpÌR}hðt¯Á¦é±ÆÅgpÂ\Å éBgpµ½R}hyÑÚµ¢ì¬û@Ít^2ÉLÚ·éBºÉÈPÈð¦·B
1.WGRIBðp¢ÄeðÍlðGRIB`®©çoCi`®ÉÏ·µoÍ·éB
2.æUÍŦµ½eðÍlÌC³ð·éB
3.³A¬i¼¬ªjA¬iìk¬ªjA³ÍA·xAμxÌÉoCi`®ÌÜÜf[^ðÂÈ°éB
4.¯¶®ìðKvÈÔ²ÆÉs¤B
CReSSÉOCÛf[^ð^¦éÆ«ÉCðt¯é̪AeðÍlªACReSSÌzèàÌlÅ é©Ç¤©Å éBmFû@ÍACReSSÌ\[XR[hðÇÝ©µ½B¡ñmFÅ«½eðÍlÌzè³êÄ¢éÅålAŬlðºÉ¦·B
E eiq_̳ij¥¥¥-1000`100000
E f[^eiqn̬x̼Aìk¼¬¥¥¥-200`200m/s
E eiq_̳ͥ¥¥0`200000Pa
E ·Ê¥¥¥123.16`2273.16K
E ·x¥¥¥123.16`333.16K
E eí¬ä¥¥¥0`100
æWÍ
@V~
[VÊ
8.1
lXeBOÉ¢Ä
3.1Åq×½æ¤ÉAÀ±BÅÍÀ±AÌoÍf[^p¢élXeBOð·éBÀ±AÌoÍf[^Í96~96~57ÂÌf[^ªoÄéBÀ±OÍiqª99~99~60¾ªACReSSÌ«¿ãAx=2`97Ay=2`97Az=2`57ÌÍÍÅoͳêéB±êðÀ±BÌúlAyÑ«EðÉ}§·é±ÆÅOÌîñðæèÝAæèðÈvZð·éªÂ\Å éB
8.2@Ï·ãÌWf[^Æynpf[^
@@À±AABÌCReSSÉæéÏ·ãÌf[^ðȺɦ·BܽAÀ±BÌÌæðÀ±AÌf[^ÌæÌɦµ½B





|
|
(x,y)=(1,1)ɨ¯éÜxEox¥¥¥kÜ35.4472xAo136.1675x
WÌÅålÆŬl¥¥¥2903.4A-1iCj
|
|
}8-1V~
[VAÌWyÑynpf[^

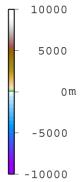

|
|
(x,y)=(1,1)ɨ¯éÜxEox¥¥¥kÜ35.7934xAo136.7665x
WÌÅålÆŬl¥¥¥3039.9A16.0
|
|
@@@@@@}8-2@V~
[VBÌWyÑynpf[^
8.3@oÍf[^Ìär
@ȺÉAABÌ9F00Æ10F00ÌñkÜ36.14xiY40jɨ¯éUi¬Ì¼¬ªjAWi¬Ì¼¬ªjAPti·ÊjAQi
öC¬äjATKEi¬GlM[j̼fÊ}𦵽BȨe}̶ãÍAÌ9F00AEãÍAÌ10F00A¶ºÍBÌ9F00AEºÍBÌ10F00Å éB
@





}8.3.1 U(m/s)
@ 



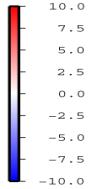
}8.3.2 W(m/s)


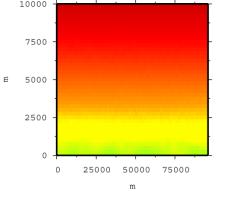


@@@@}8.3.3 Q(kg/kg)

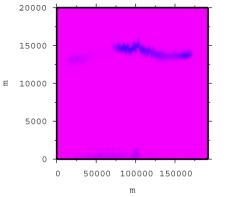



}8.3.4 TKE(J/kg)
8.3@l@
@@±±ÅÍAeðÍl̶ãÌ}ðA-9AEãÍA-10A¶ºÍB-9AEºÍB-10ÆÄÔÉ·éBܸUÉ¢ÄÍAB-10ªá±µÜÍlÆÈÁÄ¢éàÌÌAðÈðͪūĢéæ¤É©¦éBWÍB-10ª¼ÌRÂÆä×Äå«ÈlªoÄ¢éB±ê¾¯ÅÍ´öªÁèÅ«È¢ªAfððÉ·é±ÆÅAn\ÊÌp[^ª¡G»µÄ¶¶½àÌÅÍÈ¢©Æv¤BQÍAABÆàÉlªÀèµÄ¢éªABÌûªSÌIÉlªå«ÈÁÄ¢éB±êÍAðxªãªÁ½ÌÅnÊ©çÌe¿ªÍÁ«è©éªÅ«éæ¤ÉÈÁ½ÌÅAãwÉàºwÌe¿ª`íÁ½àÌÆvíêéBÅãÌTKEÉ¢ÄÍA-10ÌB-10ðä׾ç©É᤻۪©çêéB±Ì`ÍA¬GlM[Ì`ÆÄ¢éÌÅA½©öÊÖWª éðvíêéB
@@À±AÌvZÊðgÁÄÀ±B𮩷±ÆªÅ«AÌæ𬳵ĢlXeBOð®ì³¹é±ÆªÂ\ÉÈÁ½ªAðÍÊÌM«ª éÆ;¢ØêÈ¢BM«ðm©ßéÉÍAðxð·é±ÆÅN±è¤é»Ûð²×ðÍÊÆ©ä×éA½åÈCreSSÌÝèÉÖ·éÚðnlµAæèÅKÈÝèðIÔAܽÍCReSSÌvOðüÇ·éAÈǽ éB¡ñÍA½ÊÈWf[^ð³¹évOÌì¬Aynpf[^ì¬AÉÔðïâµÄµÜ¢A«ÈV~
[Vð·é±ÆªÅ«È©Á½Bµ©µAðV~
[Vð·éÛÉKvÈîÕ®õÍs¤±ÆªÅ«½B±êçðgÁÄAæèÅKÈÝèð©Â¯oµAV~
[VÊ©çÌüP_ðl¦é±ÆÅAÚIƵĢ½CÛêÌðxvZÍÂ\ÈàÌÆÈé͸ŠéB









 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ 






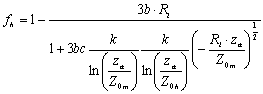

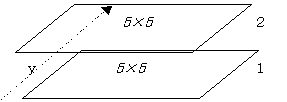



 @@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@
@@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@